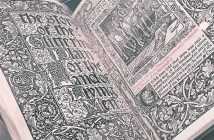Chapter 4.3
モノを捨てる罪悪感(ミニマリズムQ&A)
ミニマリズムの第一段階である「物理的に身軽になる」ということ。
これについて「モノを処分するって資源の無駄では?」「捨てるなんてもったいない」「捨てるのに罪悪感がある」というコメントをいただくことがよくあります。
たしかにモノをポイポイ捨ててしまうのには抵抗を感じるもの。地球のためにもやっぱりゴミは増やしたくないものです。
そこでまず理解しておきたいのは、処分する=捨てるではないということ。
そして、使うことがない物を後生大事に保管しておくことが「物を大切にする」ことではないのでは、とも思います。
自分(たち)だけでは食べきれない量の食材が家にあったとします。この場合、食べられる量は美味しくいただき、まわりにもお裾分けするのがよくあるパターンですね。
食べもせず放置して腐らせてしまったのに「もったいない・捨てるのは申し訳ない」とずっと大切に取っておくということはまずないはずです。
余った物を冷凍するなり加工して保存したとしても、いつかは消費期限がやってきます。
モノはそう簡単に腐ったりはしませんが、基本は同じこと。悪臭を放つなどもう使えないことがはっきりと分かるサインがないだけに、たちが悪いともいえます。
では、大量に出てくる「まだ使えるけれどもう必要ない品物」を処分するにはどののような方法があるのでしょうか。いくつかアイデアをあげてみましょう。
○売れそうな物であればリサイクルショップやオークションで売る。手数料を払えば面倒なオークション作業を代行してくれる会社もあります。
○家族や友人にたずねたり、SNSなどに投稿しもらい主を探す。
○災害地支援、海外支援のために物資を必要としている団体がたくさんあるのでコンタクトを取る。物資を寄付するための送料を負担することになっている場合もあるけれど、買い取ってもらう時間や手間をセーブし、すっきり新生活を始めるための費用と思えば安いもの。傾向として、女性服よりも男性服が不足しているようです。
○必要なくなった本は古本屋に出すほかに、ケアホームや図書館に寄付することができます。使わない文房具が大量にあったら、地元の公民館や学校などに連絡してみる。断られる場合もありますが、捨てる前に訪ねてみない手はありません。
…もし「捨てるのには抵抗があるけれど、売るための作業が面倒でモノが処分できない」「買った物を処分するのは損した気分」と感じているのであれば、こういった作業を通じて自分の生活の立て直しができることと共に「人助けができる」ということを意識してみてはいかがでしょうか。
ネイリストの女性が増えすぎたマニキュア類を買い取ってくれる人を探していたら、老人ホームで働く介護士さんがそれを譲り受けたいとコンタクトをとってきたそうです。
老人ホームで使うならばと無料で寄付したところ、ホームで暮らすお年寄りの女性たちが介護士さんからネイルをしてもらったり、お互いネイルをし合うことで気分が華やいだり会話がはずみ、ホームの雰囲気がとても良くなったと感謝されたという例もあります。
どこで、何が役立つのか分からないものですね。
私の暮らしている英国ではどの町にも必ず「チャリティ・ショップ」と呼ばれるリサイクル・ショップがあり、服や本から家電家具などの大物まで処分したいものを引き取ってくれます。寄付された品物はそこで商品として売られ、その売上げはお店の母体である慈善団体へ寄付されるシステム。品物を寄付することで税制優遇を受けることもできます。店員さんもボランティア。クリスマスなどギフトシーズンの後、英国の大掃除シーズンにあたる春には大勢の人が不要品を持ち込むので、実は新品のお買い得商品やビンテージなお宝が見つかるスポットでもあります。
「自分の家ではいらないけど、他の人が使ってくれる。そしてそれが人助けにつながる」という善意のスパイラルがひろがるシステム。日本でももっと広まるといいなと思います。こうした行動を介して思いがけない出会いも生まれそうですね。
(『あぶそる〜とロンドン』には英国チャリティーショップの舞台裏を紹介する、こんなコラムもありますよ!)
モノは使われないまま置いておけば単なるガラクタだったりタンスの肥やし。捨ててしまえばゴミ。でも、必要とされている場所にきちんと送り出してあげれば、そこでスーパーヒーロー級の活躍をすることができるのです。
ミニマリズムを取り入れるのであれば、資源の無駄もミニマムにしておきたいですね。